MMPAです。
今回は、投資でよく耳にする「ボリンジャーバンド」について解説します。
テクニカル分析を学び始めると最初に出会う指標のひとつですが、仕組みを理解すれば「相場の動き方」をとても分かりやすく捉えられるツールです。
ボリンジャーバンドの概要
ボリンジャーバンドは、株価や為替などの値動きの「振れ幅(ボラティリティ)」を示すテクニカル指標です。一定期間の移動平均線を中心にして、上下にバンド(帯)を描き、その範囲に価格が収まる確率を可視化します。
- 中心線:移動平均線(一般的に20日)
- ±1σバンド:価格が約68%の確率で収まる
- ±2σバンド:価格が約95%の確率で収まる
- ±3σバンド:価格が約99%の確率で収まる
この仕組みを利用することで、「株価が統計的にどの位置にあるのか」を判断できます。
基本的な見方
- ±2σに到達したら割高・割安の目安
- 上の+2σに触れると「買われすぎ」
- 下の-2σに触れると「売られすぎ」
→ 反発を狙う投資家が増えます。
- スクイーズ(収縮)とエクスパンション(拡大)
- バンド幅が狭まると、相場が膠着しているサイン。大きな動きの前触れとされます。
- バンド幅が広がると、トレンドが強く動き出したサインです。
- バンドウォーク
- 株価がバンドに沿って動き続ける現象。
- 上昇トレンドでは+2σに張り付きながら上がり続けることがあり、逆張りをすると早売りになることがあります。
注意点
- ボリンジャーバンドは「確率的な目安」であり、必ず反発するわけではありません。
- 強いトレンドが出ているときは、バンドを突き抜けて動くことも多く、逆張りの失敗につながります。
- そのため、移動平均線・RSI・MACDなど他のテクニカル指標と組み合わせて使うのがおすすめです。
まとめ
ボリンジャーバンドは「価格のゆらぎ」を見える化する便利なツールです。
最初は「±2σで株価が反発するか」を確認する練習から始め、慣れてきたら「スクイーズやバンドウォーク」でトレンドの発生を読み取る使い方に挑戦すると理解が深まります。
私はチャート分析をするとき、ボリンジャーバンドをよく見ています。
株価の割高・割安を判断する目安として分かりやすいからです。
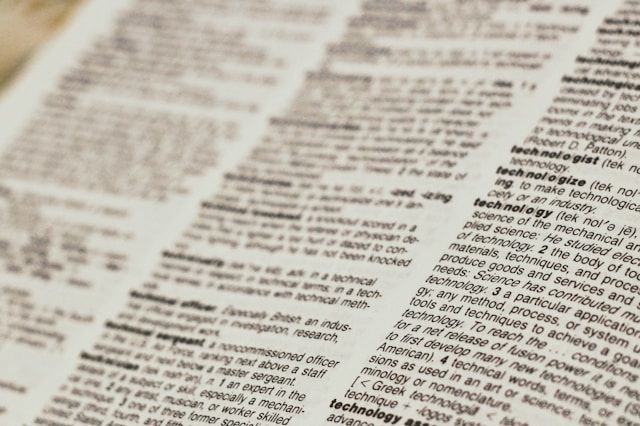


コメント